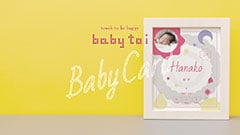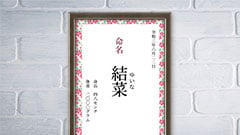名付けに関する主な行事
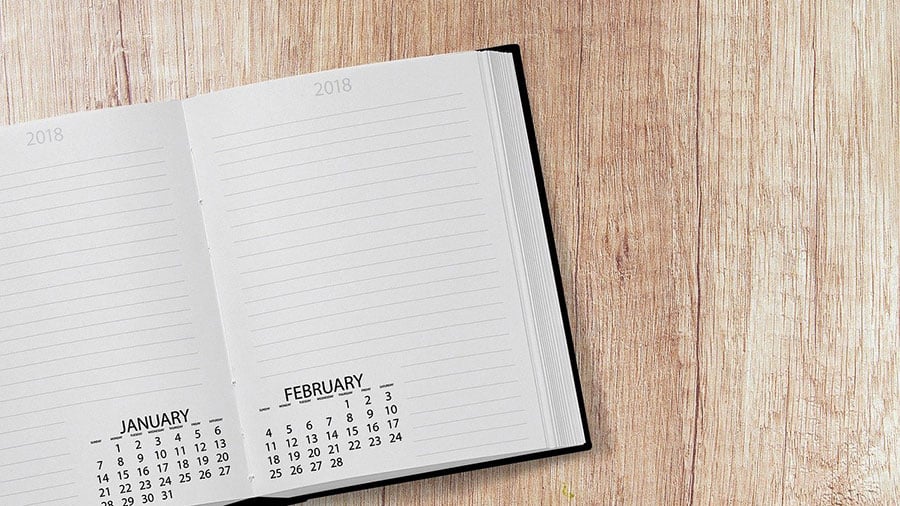
出生届やお祝い事など、名付けに関する行事やイベントをまとめました。
- 出産予定日までに名前の候補を考える
- 出産・誕生
- 生後7日目 : お七夜(おしちや)
- 生後14日目 : 出生届の提出期限
- 生後30日前後 : お宮参り・初宮参り(はつみやまいり)
- 生後100日前後 : お食い初め(おくいぞめ)
- 初節句(はつぜっく)
- 出生届について
出産予定日までに名前の候補を考える
出産予定日までに名前の候補を考えておきましょう。出産スケジュールは早産など必ずしも予定通りには行かないことが多いです。出産前後はやることも多くバタバタしますので、予定日から一ヶ月前には候補を考えておくとよいでしょう。
名前の最終決定は生まれた赤ちゃんの顔を見てという方も多く、候補から一番合う名前を見つけてあげてください。
出産・誕生
名前が決まっていたら、赤ちゃんの顔を見て、名前を呼んであげましょう。決まっていない場合は、ここからが勝負です!生まれてから名前を考える方も多く、当サイトを活用いただき、赤ちゃんにぴったりな名前を考えてあげてください。
生後7日目
お七夜(おしちや)
お七夜(おしちや)は誕生から7日目の夜に赤ちゃんの健やかな成長を願って行うお祝いです。赤ちゃんにとってははじめてのお祝いの行事となり、親戚などを招いて名前を披露する「命名式」を行うのが一般的です。
最近では出産した病院から退院する日が産後一週間前後が多いため、退院祝いを兼ねて行うことも多いです。出産後は忙しい場合も多く、あくまで記念に行うものなので、するかしないかは無理のないように決めるとよいでしょう。
生後14日目
出生届の提出期限
出生届の提出期限は、生まれた日を含めた生後14日以内です。市区町村の役所に出生証明書、出生届、印鑑、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)を持参して、出生届を提出します。役所がお休みの場合は休み明けが提出期限となります。焦ることがないよう、早めに提出するよう予定を立てておきましょう。
生後30日前後
お宮参り・初宮参り(はつみやまいり)
お宮参りは、赤ちゃんの誕生を祝い健やかな成長を祈る行事です。生後1ヵ月頃の都合の良い日を選んで神社に参拝し、赤ちゃんの誕生を祝い健康と長寿を祈ります。
一般的に男の子は生後31日や32日、女の子は32日や33日に行われるようですが、各地域で様々です。お宮参りを生後何ヶ月までにしなくてはならないという決まりはありません。赤ちゃんやお母さんの体調と相談して、良い日を選びましょう。
生後100日前後
お食い初め(おくいぞめ)
お食い初め(おくいぞめ)とは、赤ちゃんが生後100日頃に乳歯が生え始める時期に「一生涯、食べることに困らないように」との願いを込めて食事をする真似をさせる行事です。
百日祝い(ももかいわい)、真魚始め(まなはじめ)、初めて箸を使うので箸揃え(はしそろえ)、祝う時期が歯の生え始めであるから「歯がため」と呼ぶ地域もあります。
節句(はつぜっく)

「節句」は季節の変わり目のお祝いで、「初節句」は赤ちゃんが初めて迎える節句です。男の子は5月5日の端午(たんご)の節句、女の子は3月3日の桃の節句(雛祭り)に子供の健やかな成長を願い、祝います。
食い初めが済んでいない場合は1年後に延期する場合もあり、状況に合わせて検討しましょう。男の子の場合は鯉のぼり、女の子の場合は雛人形など伝統的な品物を母方の実家から贈るのが習わしですが、昨今では住宅事情などで飾りの贈り物をせずにお祝いのみを行うことが多くなっています。
出生届について
出生届(しゅっしょうとどけ)とは
赤ちゃんが戸籍を取得する手続きとして提出する書類です。生後14日以内に市町村役場または区役所に提出します。
出生届の提出期限
出生の日から14日以内(初日算入)に提出します。期限は土日・祝日を含めて数えますが、14日目が役所の休日にあたる場合は休み明けの日となります。
外国で出生した日本人(父母両方またはどちらか一方が日本国籍の場合)は、出生の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地の市区町村役所・役場に出生届と国籍留保の手続きをしなければ日本国籍を喪失する場合があります。
出生届のどこに提出しますか?
届出は、届出人の所在地、子どもの出生地、父母の本籍地のいずれかの市区町村役所・役場に行います。
出生届は誰が提出届けますか?
原則として赤ちゃんの父または母です。(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名押印)父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります。
父または母が届出できない場合、同居者または出産に立ち会った医師・助産師が届出をする必要があります。詳細は提出予定の市町村役場または区役所の戸籍係まで問い合わせてください。
出生届を提出する際に必要なもの
- 出生届(医師まは助産師等による出生証明書があるもの)
- 母子健康手帳(里帰り出産などで手元にない場合は後日持参)
- 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
出典: 法務省 出生届
あわせて読みたい
全ての名前ピックアップ&特集
-
 男女両方の名付けで使える中性的な名前男女兼用できるユニセックスな名付け
男女両方の名付けで使える中性的な名前男女兼用できるユニセックスな名付け -
 春生まれの男の子におすすめの名前
春生まれの男の子におすすめの名前 -
 春生まれの女の子におすすめの名前
春生まれの女の子におすすめの名前 -
 夏生まれの男の子におすすめの名前
夏生まれの男の子におすすめの名前 -
 夏生まれの女の子におすすめの名前
夏生まれの女の子におすすめの名前 -
 秋生まれの男の子におすすめの名前
秋生まれの男の子におすすめの名前 -
 秋生まれの女の子におすすめの名前
秋生まれの女の子におすすめの名前 -
 冬生まれの男の子におすすめの名前
冬生まれの男の子におすすめの名前 -
 冬生まれの女の子におすすめの名前
冬生まれの女の子におすすめの名前 -
 かっこいい名前特集!おしゃれで素敵な男の子におすすめの名付けまとめ【爽やか・強さ・挑戦】
かっこいい名前特集!おしゃれで素敵な男の子におすすめの名付けまとめ【爽やか・強さ・挑戦】 -
 かわいい男の子の名前特集!みんなから愛されるおすすめの名付けまとめ
かわいい男の子の名前特集!みんなから愛されるおすすめの名付けまとめ -
 かわいい名前特集!女の子におすすめの名付けまとめ【ふわふわ感・色彩・気品】
かわいい名前特集!女の子におすすめの名付けまとめ【ふわふわ感・色彩・気品】 -
 センスのいい「知的・クリエイティブ」のイメージを持つ男の子におすすめの名前
センスのいい「知的・クリエイティブ」のイメージを持つ男の子におすすめの名前 -
 センスのいい「おしゃれ」をイメージする女の子におすすめの名前
センスのいい「おしゃれ」をイメージする女の子におすすめの名前 -
 花の名前をモチーフにした女の子の名付け
花の名前をモチーフにした女の子の名付け -
 キラキラネームじゃない、珍しい・個性的で変わった印象を与える男の子の名前まとめ
キラキラネームじゃない、珍しい・個性的で変わった印象を与える男の子の名前まとめ -
 キラキラネームじゃない、珍しい・個性的で変わった印象を与える女の子の名前まとめ
キラキラネームじゃない、珍しい・個性的で変わった印象を与える女の子の名前まとめ -
 色彩をテーマにした男の子の名前まとめ
色彩をテーマにした男の子の名前まとめ -
 色彩をテーマにした女の子の名前まとめ
色彩をテーマにした女の子の名前まとめ -
 誕生石・宝石をテーマにした女の子の名前まとめ
誕生石・宝石をテーマにした女の子の名前まとめ -
 柔らかい響きで穏やかで優しい印象の名前に。長音(ちょうおん)が入る男の子におすすめの名前
柔らかい響きで穏やかで優しい印象の名前に。長音(ちょうおん)が入る男の子におすすめの名前 -
 柔らかい響きで穏やかで優しい印象の名前に。長音(ちょうおん)が入る女の子におすすめの名前
柔らかい響きで穏やかで優しい印象の名前に。長音(ちょうおん)が入る女の子におすすめの名前 -
 スタイリッシュで現代的な印象の名前に。拗音(ようおん)が入る男の子におすすめの名前
スタイリッシュで現代的な印象の名前に。拗音(ようおん)が入る男の子におすすめの名前 -
 スタイリッシュで現代的な印象の名前に。拗音(ようおん)が入る女の子におすすめの名前
スタイリッシュで現代的な印象の名前に。拗音(ようおん)が入る女の子におすすめの名前 -
 健康で活発な印象の名前に。撥音(はつおん)が入る男の子におすすめの名前
健康で活発な印象の名前に。撥音(はつおん)が入る男の子におすすめの名前 -
 活発でキュートな印象の名前に。撥音(はつおん)が入る女の子におすすめの名前
活発でキュートな印象の名前に。撥音(はつおん)が入る女の子におすすめの名前